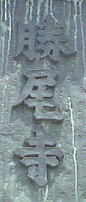 勝尾寺表参道
勝尾寺表参道
勝尾寺(かつおうじ)へ向かう参道は、新家の大鳥居を基点として、 北へ向かう36町(約4km)の道が表参道(旧参道)です。箕面市栗生 新家の国道171号から南へ30mほどの西国街道に面した三差路に石造り の大鳥居が立っています。ここを基点として参道沿いには勝尾寺への 距離を示す町石が残されています。いにしえの時代から数え切れない ほどの参拝者が、この町石を目印に山へ向かったことでしょう。 今回マウンテンバイク(MTB)でこの参道を上がってみました。 勝尾寺参道周辺地図 (JPEG 22k)
 |
現存する石の大鳥居は寛文6年(1666年)に建て られたものですが、勝尾寺文書には鎌倉時代の 寛元3年(1245年)に木の鳥居が建てられたこと が記録されています。 額に「勝尾寺」とあります。 (この画面上の文字です) 傍らの町石には刻まれた「三十六町」の文字が 読めます。 この日の大鳥居周辺は道路工事中でした。
 |
この町石を過ぎるといよいよ山道の参道になります。 「三十六町」から「八町」までは江戸時代中期に建て られました。傾いた石柱が歴史を感じさせます。
 |
七町から山門の前までの八基は「五輪塔」の形をして います。鎌倉時代の宝治元年(1247年)の作で今も完全 な姿を残すのは「一町」と「二町」の2基です。 現存する町石では最古として、国の史跡に指定されて います。
 |
寺は「かつおうじ」と読みます。古文書によ れば、第六代座主行巡上人の祈りで清和天皇 の病が治り、祈願力には時の朝廷の権力も及 ばなかったことから王に勝つ寺「勝王寺」の 号を授けられたといいます。 足利尊氏ら戦勝を願う武将たちも寺を保護し その恩恵にあずかろうとしました。
 |
今は、受験生、選挙の候補者、スポーツ選手などが 勝利を願って祈っています。 境内の屋根や塔などあちこちに小さなダルマが無数 に置かれています。
 |
源頼朝が再建したと伝えられる勝尾寺最古 の鎌倉時代の建物です。堂内の薬師三尊は 俗に泣き薬師とも云い眼病を治して頂ける 薬師さんとして知られています。 この三尊は50年に1回御開帳の秘仏です。